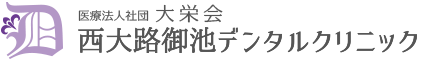麻酔の日に知っておきたい麻酔の種類について

こんにちは。西大路御池デンタルクリニックです。
10月13日は「麻酔の日」でした。1804年のこの日、日本人医師・華岡青洲が世界で初めて全身麻酔を用いた手術に成功し、その偉業を記念して制定されました。
今回は、この記念日にちなみ、歯科治療で使われる麻酔の種類や副作用、麻酔後の過ごし方についてお話しします。
麻酔の主な種類
歯科治療で使われる主な麻酔は以下のとおりです。
表面麻酔
注射針を刺すときの痛みをやわらげるために行う麻酔です。歯ぐきの表面に薬を塗って感覚を一時的に麻痺させ、数分ほど待って効果が出てから治療をはじめます。これは「2段階麻酔法」の1段階目にあたり、この後に行う注射による麻酔をより快適に受けられるようにするための処置になります。
浸潤麻酔
むし歯の治療や神経の処置、歯を抜くときなどに最も一般的に行われる麻酔です。歯ぐきに直接麻酔を注射し、治療部分の痛みをやわらげます。注射の刺激を減らすために極細の針を使用したり、薬液を体温に近づけたりする工夫も行われています。
伝達麻酔
親知らずの抜歯や下顎の奥歯の治療など、広い範囲にしっかりと効かせたいときに行われる麻酔です。顎の神経の近くに麻酔を行うため効果が長く続き、治療中の痛みを大きく抑えることができます。
麻酔による副作用について
麻酔によっては副作用が発生することもあります。
表面麻酔では、まれに眠気やめまい、吐き気が出ることがあります。
また、浸潤麻酔や伝達麻酔では、手足のしびれや震えを感じる場合もあります。ほとんどは一時的なもので、しばらく横になって休むことで自然におさまることが多いですが、症状が続く場合はご相談ください。
なお、麻酔薬にアレルギーがある方や、過去に副作用を経験された方、持病がある方は、必ず事前に歯科医師へお伝えください。特に、一部の麻酔薬に含まれるアドレナリンは、血圧の上昇や動悸の原因になることがあるため、高血圧や心臓の病気をお持ちの方には特に注意が必要です。
麻酔の効果時間はどのくらい?
麻酔は種類によって持続時間が異なります。
- 表面麻酔 … 約10〜20分
- 浸潤麻酔 … 約1〜3時間
- 伝達麻酔 … 約3〜6時間
治療後も、麻酔の種類によっては数時間にわたり効き目が残ることがあります。そのため、しばらくの間は麻酔が続いている点に注意してください。
麻酔後の過ごし方
麻酔が効いている間は、感覚が鈍くなり痛みを感じにくくなります。この状態で食事をすると唇や頬、舌をうっかり噛んでしまう危険性があるため、麻酔が完全に切れるまでは、食事を摂らないことをおすすめします。
また、熱い飲み物もやけどの原因になりやすいので、麻酔が残っているときは常温や冷たいものを選ぶと安心です。
安心して麻酔を受けるために
麻酔は、治療中の痛みをやわらげ、患者さんが安心して治療を受けられるようにする大切な手段です。麻酔の種類ごとに特徴や効果の持続時間、副作用が異なりますので、あらかじめ正しく理解して備えておくことで、不安をやわらげることができます。
当クリニックでは、患者さん一人ひとりの状態に合わせて最適な麻酔方法をご提案し、安心して治療を受けていただけるよう努めています。ご質問やご不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
初診WEB予約
むし歯治療をはじめ、小児歯科・入れ歯・インプラント・セラミック治療・ホワイトニングなど、各種治療に対応。
お気軽にお問い合わせください。